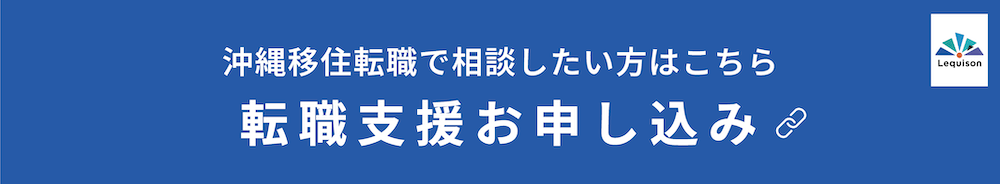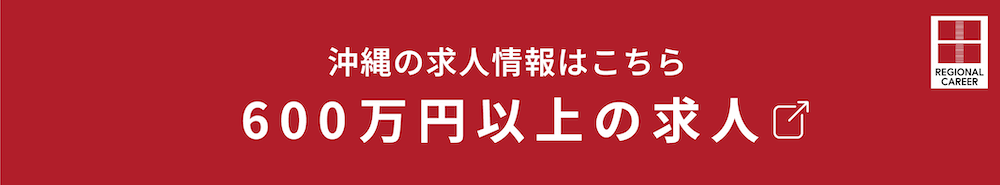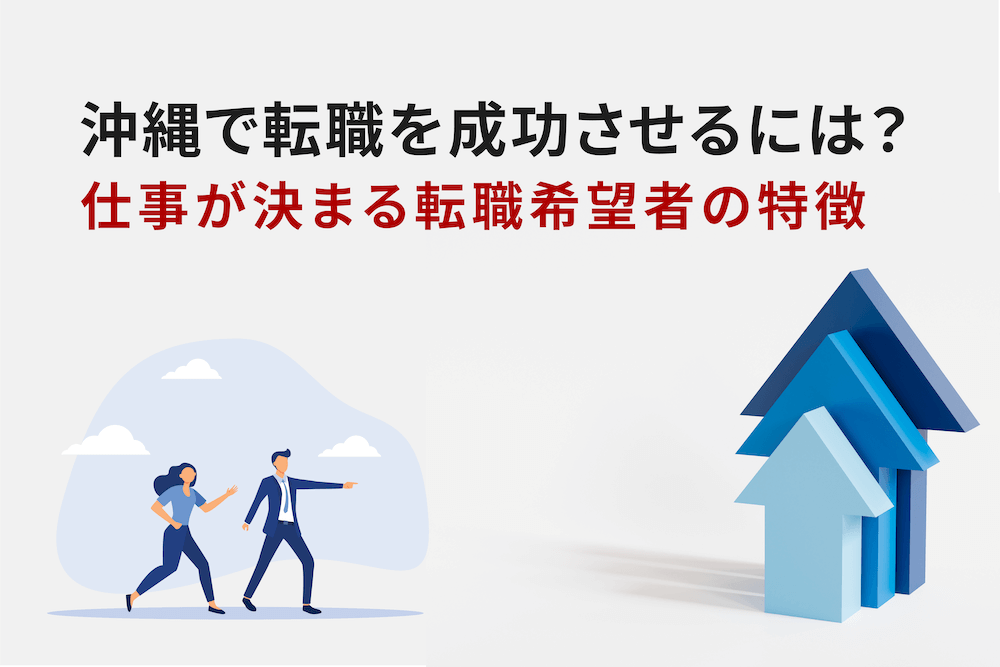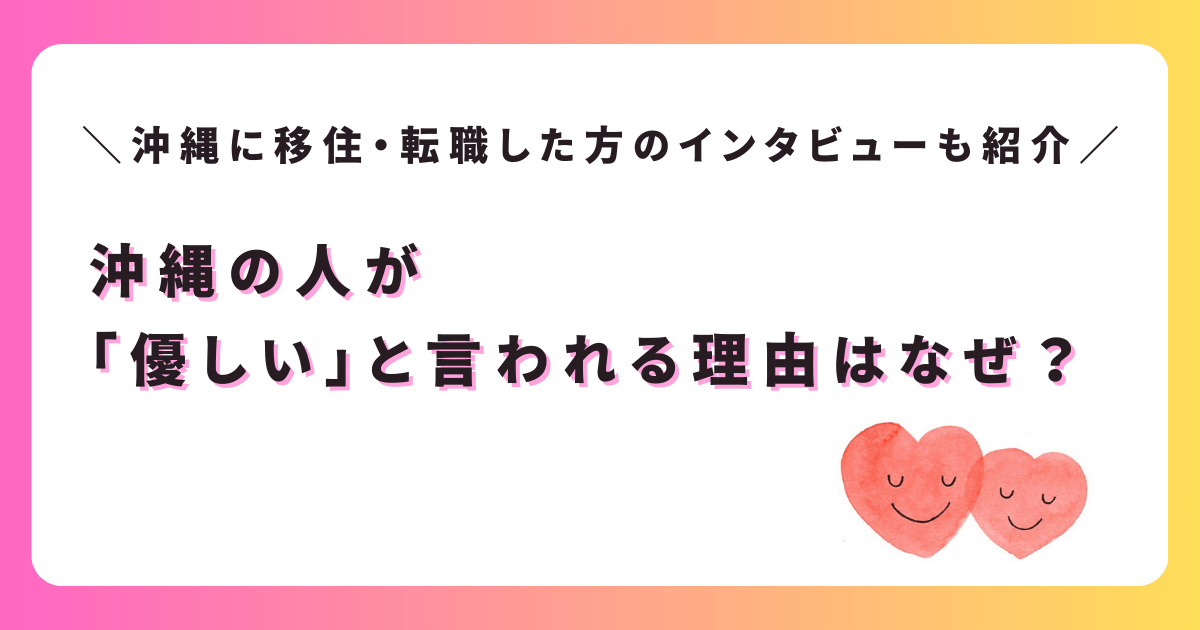沖縄の課題を「バイオ×IT×観光」で解決する企業たち ―社会的活動の最前線とUIターン転職の可能性―
こんにちは。株式会社レキサン リージョナルキャリア沖縄の玉城です。
私は沖縄転職エージェントのコンサルタントとして、企業の採用や人事だけでなく、その企業が取り組む“社会的な活動”や“組織の姿勢”を深く知る機会があります。外から見えにくい部分も、プロジェクトの実態や経営陣の考え方を直接確かめられるのは、コンサルタントという立場ならではです。
そこで今回は、私が実際に担当させていただいているIT業界関連で「バイオ」「IT」「観光」という三つの柱を軸に、地域課題の解決に挑むユニークな企業の事例をご紹介します。沖縄の未来を創る仕事に興味を持つ方に向けて、その社会的意義や魅力が少しでも伝われば幸いです。
バイオ産業が切り拓く沖縄の未来

Jブルークレジット®認証を取得したTOPPANデジタルの「ICT KŌBŌ®」
まず注目したいのは、TOPPANデジタルが展開するサテライトオフィス「ICT KŌBŌ®」です。全国各地で地方創生やDX推進を目指す同社は、沖縄県うるま市の拠点にてモズク養殖と環境保全を融合させたプロジェクトを進めています。特に大きな話題を呼んだのが、モズクが海中でCO2を吸収する“ブルーカーボン”認証を受け、2025年初頭に国内初となるモズクの「Jブルークレジット®」を取得した点です。モズクが21.7トンものCO2削減効果を認められたことは、養殖業に新たな価値をもたらしました。
この取り組みを支えるのが、同社独自の漁業DXソリューション「InnoReef®」です。これはAI技術を用いた品質判定や重量管理アプリ、さらには藻場面積の測定などを通じて生産効率と環境保全の両立を目指すプラットフォームです。漁業現場では経験や勘に頼りがちな作業工程が多い中、ITによってデータを“見える化”し、持続可能な形でモズクの栽培を行っています。まさにバイオ資源を活かしながらITを導入し、沖縄の水産業を革新している好例と言えます。
泡盛粕を活用した革新的フードテック「うま藻(UMAMO)」
バイオ分野でさらに注目したいのが、アルガレックスです。2021年に設立された若いフードテックベンチャーながら、泡盛の製造工程で生じる粕を使って藻を培養するというユニークな研究開発を進めています。こうして誕生したのが、高DHA含有量と豊かな旨味を兼ね備えた「うま藻(UMAMO)」です。これは泡盛の粕に含まれるアミノ酸などが藻の栄養源となり、通常よりも高い栄養価を実現するという仕組みです。
もともと藻は“養殖の飼料”として期待されていた反面、「人が食べるほどの魚を輸入し、それを飼料にしている現状」に対して疑問を抱いたのが開発のきっかけでした。アルガレックスでは、「藻を飼料化することで輸入依存を減らし、さらに人間にも役立つ新食材を作れないか」という考え方を実証しています。沖縄伝統の酒造文化×最先端のバイオテクノロジーという異業種融合の可能性を示し、県内外のフード産業関係者からも熱い注目を集めています。
海洋深層水を生かす化粧品メーカー「ポイントピュール(ryuspa)」
沖縄のバイオ活用といえば、ポイントピュール(ryuspa)も外せません。久米島の海洋深層水を中心に、月桃やアロエベラ、グァバなどの沖縄特有の植物資源を化粧品へ配合し、“沖縄ならではの美容”を発信しています。特に深層水に含まれる豊富なミネラルは保湿やバリア機能向上が期待され、社内には専門の研究チームを設けて久米島町海洋深層水研究所との連携も積極的に行っており、「ディープシーウォーターエキス」という独自素材の開発に取り組んでいる点が特に興味深いです。
また、同社では“赤土(クチャ)”など、沖縄の伝統的な美容素材も現代的にアレンジした商品開発を続けており、観光客からの人気も高まっています。こうした地域資源の活用は、環境に負荷をかけずに高付加価値な製品を生み出し、沖縄のバイオ産業を国内外へ広げる大きな原動力となっています。
沖縄県ではバイオ関連産業の振興に力を入れており、県内のバイオ関連企業の数は2011年は32社でしたが、2024年には106社と大きく伸びています。
その背景には、県の支援によるインフラの整備やOISTの存在の影響も大きいかと思います。他の都道府県と比べると特に、OISTやインキュベート施設を活用したスタートアップ支援が特徴です。
こういった状況を背景に、沖縄へのUターン希望者にとっては、「新たな価値創造」に携われることが魅力であるといえます。
ITが生み出す新たな産業のかたち

okicomの「Bagasse UPCYCLE」と伝統工芸DX
次に、IT×DXによる沖縄の課題解決を牽引するのが株式会社okicomです。同社が取り組む「沖縄DXプロジェクト」の中から、特に注目すべき革新的な取り組みについて詳しくご紹介します。まず一つは、サトウキビの搾りかす(バガス)を活用したかりゆしウェア「Bagasse UPCYCLE」です。製造工程で生じる廃棄物を有効利用するだけでなく、ICタグを取り付けることで原材料や製造履歴を一元管理し、さらに環境貢献度を可視化する仕組みを導入しています。2023年度にはRFIDによる在庫管理システムを高度化し、800着規模のICタグ情報を一度に読み取り可能とするなど、効率とサステナビリティを両立させている点が特に注目を集めています。
もう一つの伝統工芸DXは、沖縄の文化的財産を守りつつ収益化を目指す試みです。1300年代起源の伝統工芸「琉球びんがた」は、従来“染工賃”のみが収入源で、図案そのものの価値が評価されづらい構造でした。okicomでは琉球びんがた普及伝承コンソーシアムの事務局を務め、型紙をスキャンしてデジタルデータ化、さらにはNFT発行による二次流通など、まさに最先端のIT技術を導入することで職人へライセンス収入を還元しています。加えてオンライン化により、これまで年間30件程度だった対応可能案件を倍増する見込みで、職人や工房の持続的な経営を支える重要な役割を果たしています。
琉球大学と共同開発した運転代行配車アプリ「AIRCLE」
沖縄特有の交通事情に挑むスタートアップとして、Alpaca.Labが運営する運転代行配車プラットフォーム「AIRCLE」は革新的です。沖縄の飲酒運転率が全国ワーストという深刻な課題に対し、AIアルゴリズムを活用した迅速な配車システムを導入し、電話予約の待ち時間や混雑を大幅に削減しました。
特に注目すべきは、既存の運転代行業者を巻き込んだ業務支援クラウドの提供です。手書きで行われていた受注や帳簿管理をデジタル化することで、業務効率や正確性が飛躍的に向上するとともに、ドライバーの働きやすさも改善されています。結果として女性ユーザーの利用拡大にもつながり、現在では沖縄以外の複数都市にサービスを展開中。短期間で国内最大級の運転代行配車アプリへと成長しつつある点は、ITを使って社会課題を解決し、さらにビジネスとしても拡大可能であることを証明していると言えます。
うむさんラボが目指す“株式会社沖縄県”というビジョン
もうひとつITと社会課題解決の融合が顕著なのが、うむさんラボです。沖縄県うるま市に本社を置く経営コンサルティング企業でありながら、たった9名の組織で「わたしたちは、豊かさを分かち合える逞しくて優しい経済の循環を生み出すことで、自然とひと、人とひととがありのままでともにある社会を創造します」という壮大なミッションを掲げています。
特徴的なのが、沖縄全体を一つの会社に見立てて発展させていこうとする「株式会社沖縄県」というキーワードです。ここには、県内の多様な主体が協力して経済的・社会的価値を創出していく、という思想が込められています。
うむさんラボが提供するサービスの中で特に注目すべきは、中小企業向けのバックオフィス業務アウトソーシング「ゆいといろ」です。シングルマザーや発達障がい者、シニアなど社会的マイノリティのメンバーがチームで業務を支援する仕組みで、企業側は高度な管理部門を整備しなくてもノウハウやリソースを得られるメリットがあります。働き手側も、特性を補い合いながらスキルを磨き、所得向上を図れる点が魅力となっています。
また、同社は「うむさん基金」や「カリーファンド」などの形で社会的インパクト投資を進めており、ITリテラシーやマネジメントスキルを活かして、県内外の課題解決型ビジネスを資金面でもサポートする仕組みを構築中です。地元の経営者だけでなく、UIターン希望者にとっても“地方でこそ生まれるイノベーション”を体感できる企業と言えるでしょう。
かつての沖縄のIT業界では「首都圏案件の下請け」が主で、社会に対して新しい価値を創造するような仕事は少なかったのですが、近年では一次請けや強力な価値を提供できるベンチャー・スタートアップが少しずつ増えてきています。
沖縄ローカルの地域課題に対して最新テクノロジーで解決にチャレンジしている企業もあり、こういった状況を背景にUIターン転職者様にとっても魅力あるポジションが増えています。実際にUIターン転職希望者様の面談においても「こういう魅力ある企業があるとは知らなかった」というご感想をよくいただいております。今後も魅力ある企業や取り組みの増加が期待できます。
観光×文化で沖縄の可能性を拡張する

1.ヘリコプターを“バス”にする「ヘリバス」構想
観光産業と聞くと、宿泊施設や飲食業に目が向きがちですが、Blue Mobilityの「ヘリバス」はその固定観念を覆す存在です。小規模スタートアップながら、那覇空港・恩納村・名護市を結ぶヘリコプターの定時運航を始め、移動時間を2~3時間からわずか30分へと短縮。しかもダイナミックプライシングによる価格調整を行い、富裕層向けの高級ツアーだけでなく“大衆化”へ挑戦しています。
この取り組みは観光客の移動時間短縮による滞在満足度の向上だけでなく、交通渋滞や二次交通不足といった地域の課題を解決できる可能性があります。さらに、災害時には物流や医療搬送の手段として活用できるなど、社会インフラとしての意義も非常に高いです。沖縄振興開発金融公庫や地元銀行が創業融資を行うなど、行政や金融機関からの期待値も大きいことがうかがえます。
2. 後継者不足に挑む老舗酒造支援の南島酒販
観光資源の一つでもある“泡盛文化”を守るために果敢な取り組みを行うのが南島酒販です。創業40年超の酒類卸売業者でありながら、若者向けリキュールの開発や他酒造との共同研究「shimmer(シマー)プロジェクト」を展開し、泡盛の新たな魅力を発信。さらに、経営が厳しくなった老舗酒造を支援し、「識名酒造」の経営権を譲渡されることで伝統的な酒造文化を守る活動も積極的に行っています。
大岩社長の「目の前の利益よりも長期的に泡盛業界を活性化させたい」という理念は、地域産業の存続に大きな意味を持ちます。また、同社は「沖縄の役に立つ会社でありたい」という創業時からのモットーに基づき、休日120日と残業ゼロを目指す働き方改革や給与所得向上の取り組みを進めており、社員の定着と産業振興の両面から地域に貢献しています。
3. 「まちなか留学」で多文化を体感するHelloWorld(ハローワールド)
沖縄はアメリカ軍関係者をはじめ、多数の外国籍住民が在住する“多文化地域”としても知られます。そこで革新的なサービスを提供しているのがHelloWorld(ハローワールド)です。同社の「まちなか留学」は、県内に住む外国人家庭へ24時間ホームステイできるプログラムで、子どもたちがリアルな異文化体験を通して英語やコミュニケーションスキルを学ぶ仕組み。60ヶ国以上の文化が選択可能という点が従来の留学とは大きく異なり、世界規模の多様性を沖縄で“疑似体験”できるのが特徴です。
加えて、生成AIを活用した教育プラットフォーム「WorldClassroom」や、那覇国際通りを舞台にする「まちなかENGLISH QUEST」など、エンタメ要素を取り入れながら英語教育と異文化理解を促進。これらの活動は単に観光客を楽しませるだけでなく、地域に暮らす外国人の存在を“生きた教材”として活かす仕掛けづくりにもつながっています。
4. 伝統工芸と市場拡大に挑む「ゆいまーる沖縄」
最後に、工芸品の視点から地域文化を深く守り育てるゆいまーる沖縄にも触れておきましょう。1988年の創業以来、単なる卸売ではなく生産者の課題解決に伴走する姿勢が特徴で、「工芸品は売れるのか?」という根本的な壁に挑んできました。例えばブランド概念の導入やオンラインでの販路開拓など、工芸そのものを“稼げるビジネス”として成立させる支援を行うことで、後継者不足の解消や文化存続を後押ししています。
また、経済性だけでなく「どう文化を紡ぎ、未来に残すか」というテーマを大切にしている点が特に注目を集めます。「稼げる仕組み」をつくりながらも、職人のモチベーションを高め、地域の文化価値を発信することで、観光立県としての沖縄の魅力も増幅しているのです。
観光産業の領域においても、ヘリバスのように“空を移動インフラ”と位置づけたり、酒造文化や多文化共生をキーワードにした取り組みが活発です。伝統や歴史を持つ企業が新しいチャレンジを行い、スタートアップが既存の概念を覆す活躍をしています。また、多くの場所で言われていることですが、観光において「消費」だけではなく「体験」を通じた価値提供も今後もっと増えていくのではないかと感じました。その結果として、国内外からの観光客だけでなく、沖縄に暮らす人々にとっても価値を高めるサービスが生まれています。
まとめ
沖縄には「バイオ」「IT」「観光」の三大産業領域を軸に、地域課題に正面から向き合う企業が数多く存在します。社会的意義の大きい仕事に携わりたい方にとって、沖縄は挑戦できる領域が広がる宝庫とも言えるかもしれません。「住む場所」や「観光として」注目されてきた沖縄ですが、「働く場所」としても魅力的になっていくのではないでしょうか。
我々は転職コンサルタントとしてこういった沖縄の魅力ある企業やお仕事の情報を適切に発信しつつ、UIターンを通じて地域に貢献したいという方々の後押しを続けていきたいと考えています。
このような社会問題の解決に取り組む沖縄企業への転職にご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。