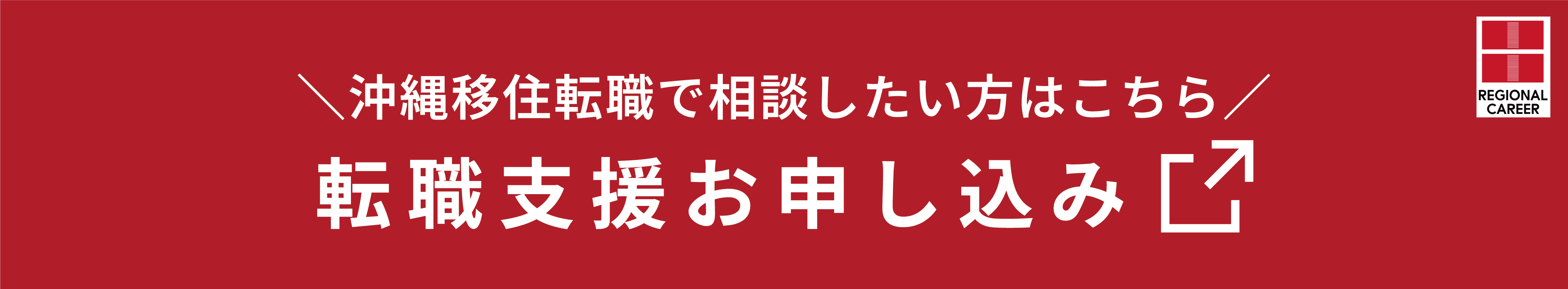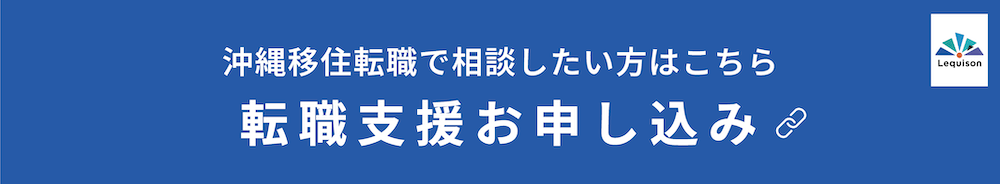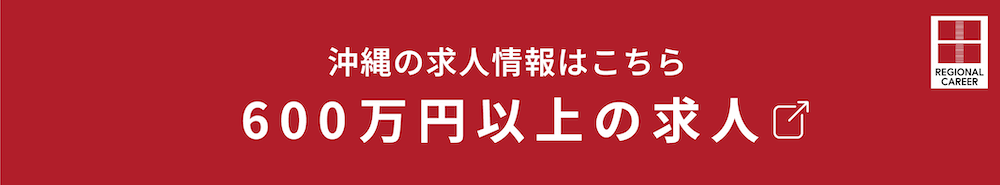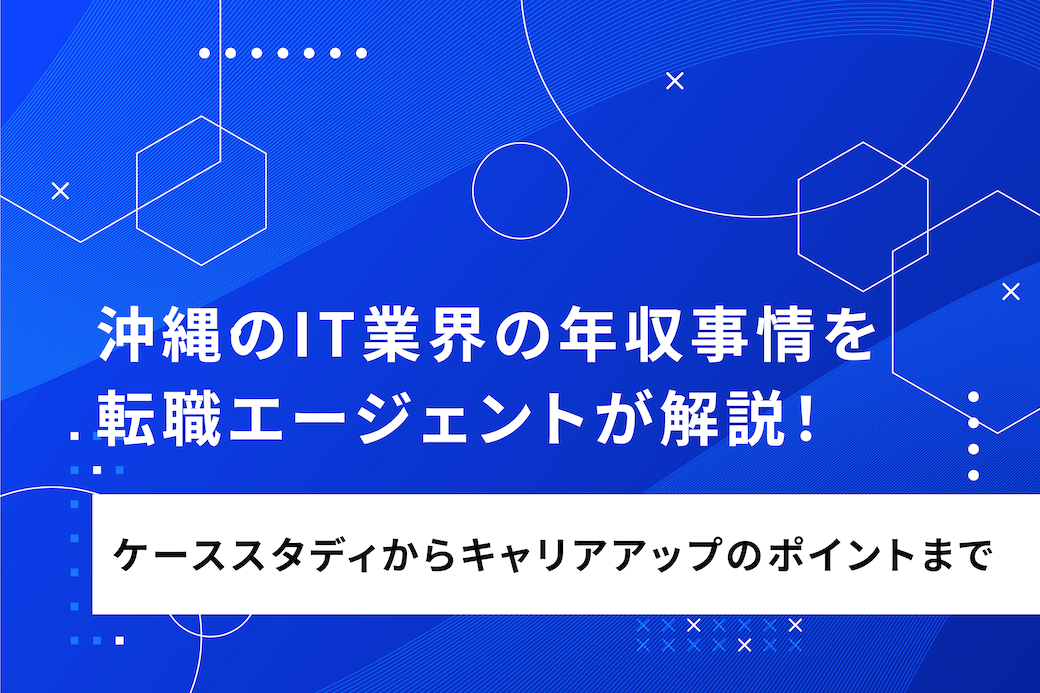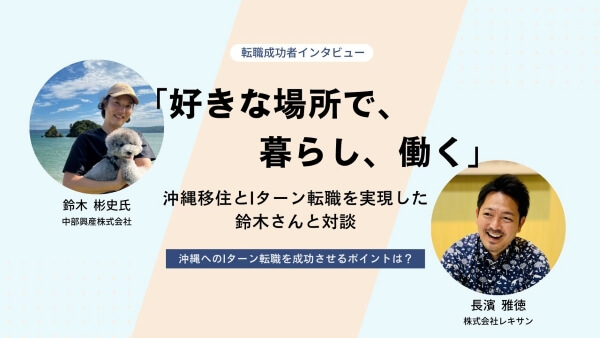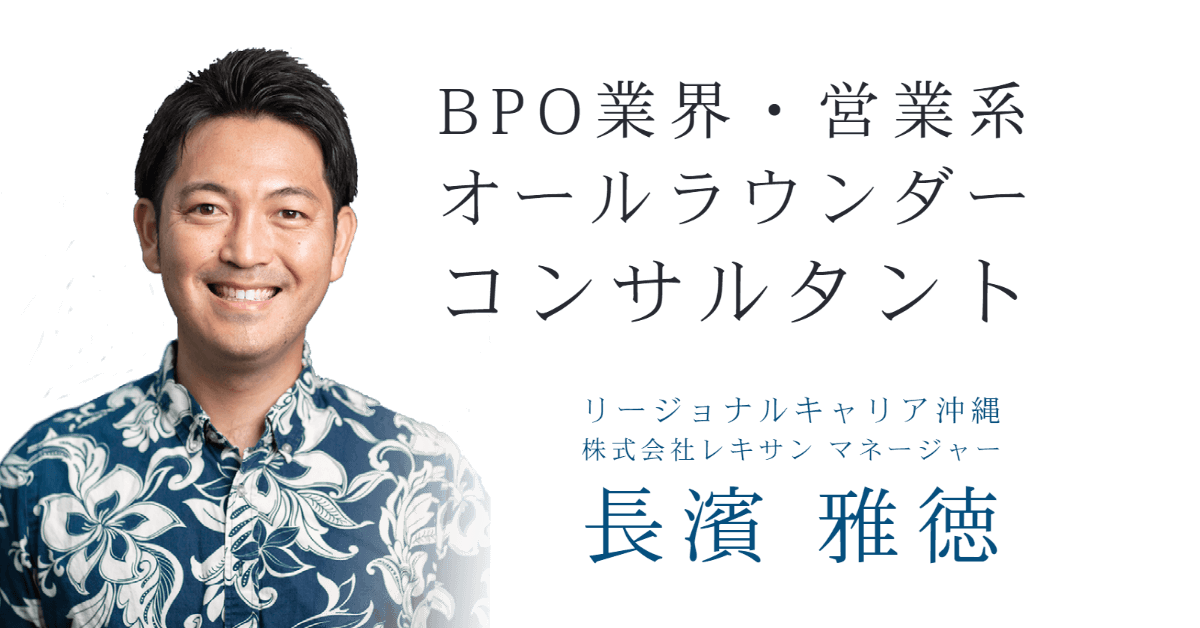転職活動はAIで変わる?ChatGPTで自己分析・職務経歴書を効率化する方法と活用ポイント
ここ数年で、AI技術は私たちの生活に一気に広がり、転職活動のスタイルも少しずつ変わってきました。
「便利そうだけど、実際どう使えばいいの?」「AIだけに頼って大丈夫?」——そんな声もよく耳にします。
こんにちは。株式会社レキサン(リージョナルキャリア沖縄)の玉城です。
今回はIT担当コンサルタントの目線から、AIを活用した転職活動について具体的な方法とポイントを解説します。転職活動の第一歩を踏み出すハードルを下げるとともに、最終的にはAIと沖縄の転職エージェントを上手に併用し、よりスムーズな転職を目指しましょう。
職務経歴書のAI活用 — 簡単かつ的確に“自分”を伝える

■生成AIで職務経歴書を作成・ブラッシュアップするメリット
転職活動において職務経歴書の作成は非常に重要ですが、手間がかかる作業でもあり、慣れていないとなかなかスムーズに進めるのが難しい場合もあります。
中途採用は生ものであり、タイミングやご縁が非常に大事なので、職務経歴書の作成の遅れが原因で転職を一歩前に踏み出せなかったり、書類提出に時間がかかってしまうと機会損失にもつながってしまいます。
そこで、生成AIを活用することで少しでも職務経歴書の手間を減らし、なおかつ内容の質を適切に向上できないかと思い、今回の記事をまとめました。
■GPTsを使った作成
まず、比較的手軽に始められるAIを使った履歴書の作成方法として「ChatGPT」をご紹介します。
ChatGPTとは、OpenAIという企業が提供する対話型AIのことで、まるで人と会話をするように質問をしたり、相談をしたりできるサービスです。最近では仕事や就職活動でも活用される場面が増えています。
さらにこのChatGPTの中には「GPTs(ジーピーティーズ)」と呼ばれる“カスタマイズされた専用AI”が数多く公開されています。GPTsとは、特定の目的に特化して調整されたChatGPTの応用版で、例えば「職務経歴書の作成サポート用」など、使いやすく最適化されたものもあります。履歴書や職務経歴書の作成に関しても、こうしたGPTsを活用することで、よりスムーズに書類作成が進められるでしょう。
また、ChatGPTやGPTs以外にも、履歴書作成に活用できるツールがあります。たとえば「sayhi2.ai」は、職務経歴書専用のツールではないものの、「職務経歴書を作りたい」といった要望を入力するだけで、AIが丁寧に対応してくれる便利なサービスです。専門的なカスタマイズがされているわけではありませんが、ざっくりとした使いやすさは感じられます。
このように、基本的なChatGPTを活用する方法、目的特化型のGPTs、あるいはsayhi2.aiのようなAIツールデータベースもあります。
では、ここからは私が実際にChatGPTを使って職務経歴書を生成する中で感じた点とポイントをご紹介します。
ポイント1. 基本的な構成
職種ごとのフォーマットはGoogle検索などで探せます。ですが、職種によってはなかなか良いフォーマットがみつからなかったり、フォーマットを見てもイマイチ書き方が分からなかったりします。
そこで、まずは自分の職種を前提にして「どのような構成にすべきか?」「注意点は何か」をChatGPTへ質問しました。これによって職務経歴書の枠組みを考えます。
ポイント2.文章表現の最適化
構成を作成後、ある程度職務経歴書の中身も入れ込んだ段階で、「この内容は志望する業界や職種に合っているか?」「もっと適切な言い回しはないか?」といった観点で、ChatGPTにレビューを依頼してみます。志望する業界や職種などをAI側に伝えながら適切な表現になっているかを確認するとよいかもしれません。
また、業界や職種を跨いだ転職になる場合、他業界・他職種の方にも理解してもらいやすいような表現や説明などが必要になります。そこからさらに「なぜ自分が志望先の企業へ価値貢献できるのか」を説明したり示唆を与えるような内容にしていくと効果的だと感じました。
ポイント3.“新しい気づき”を得る質問
さらに、作成した職務経歴書の内容からどういった業界・職種だと可能性がありそうか質問してみるのも良いかもしれません。
「自分の経歴から特に活かせそうな職種は?」
「エンジニア×沖縄でできる挑戦は?」
などの切り口でAIに問いかけることで、自分でも気づいていなかった強みや可能性に出会えることがあります。
以上のポイントを踏まえ、業務実績・スキルセットを箇条書きにしてAIへ入力し、推敲された内容を読み込んで不要な表現を削除したうえで、自分の言葉に再構成しました。
生成AIの種類や利用プランにもよりますが、名前や住所などの個人情報は極力入力しないようにしましょう。履歴書や職務経歴書に関わる部分だと、氏名、住所、電話番号、生年月日、年齢、性別などが該当します。
■所感と転職エージェント目線でのアドバイス
生成AIを活用することで、まずは一歩目の大まかな内容の作成はできたと思います。
大切なポイントは、自分の考えを自分の言葉で表現し肉付けすることです。生成AIによって大まかな業務内容は作成できますが、自分の言葉を入れることでオリジナリティが増してより良い職務経歴書となります。
一方で、生成AIでは難しい部分も感じられました。それは自分自身や業務内容の深堀りです。概要までは簡単に作成できますが、生成AI側から質問された内容を記載していく形だと表面的になりがちです。
具体的には、「自分の成果を自分で認識していない場合」や「課題解決のストーリーを思いつかない場合」です。
AI側から実績や課題解決のストーリーの記載を求められても、自分では気づけず、書けないこともあります。
そういった場合は、他者からこれまでの仕事の流れや経験などを丁寧に質問してもらうことで、自分が提供してきた価値に気づけるようになります。
このように、生成AIを利用しても自分で内容に深みや具体性を出すことが難しい場合は転職エージェントの活用など、人との会話を通して深堀りを支援してもらうと有効でしょう。
企業リサーチ

■企業情報収集にAIを使うメリット
みなさんも企業との面接前には企業に関する情報収集をされているかと思います。
Google検索でも収集は可能ですが、生成AIを使えばニュース記事やプレスリリースなど膨大な情報を要約・抽出し、短時間で整理することができます。
生成AIを使って大まかな情報を把握しつつ、ホームページなどでより詳細な調査をするとよいでしょう。
また、最近発達してきている「推論系」のAIを活用することで、分析作業の省力化も可能になってきています。推論系とは、単なる情報の要約や抽出ではなく、背景や文脈を踏まえて仮説を立てたり、因果関係を推測したりといった“考える力”を持つAIを指します。一方で、非推論系のAIは、既存の情報から回答や要約を生成することは得意ですが、自ら新たな視点を提示したり、複雑な問題に対して洞察を加えるのは難しいとされています。
推論系AIを使うことで、競合他社の比較、短期や中長期の戦略、課題などの分析がある程度可能です。こういった分析を通じて、企業の課題に対する仮説を立て、その課題に対して自分がどういう価値を発揮できるか、あるいは面接などで何を質問すべきかを整理するのに役立ちます。
実際に推論系とそうではないモデルで比較してみましたが、推論系の方がより示唆を富んだアウトプットを返してくれました。
■実際にAIを使ってみた感想
情報収集と分析の仕方が変わり、かなりスピードが上がったと思います。以前であればインターネット上の様々な情報の中から情報を取捨選択し必要な情報を集めなければなりませんでしたが、それがとても効率化されたように思います。また、AI側の分析を元に示唆を得ることもできるので、優秀な秘書がいるような感覚です。
一方で、AIが集めてきた情報の信憑性のチェックやAIが集められなかった情報にはアクセスできていない可能性については注意が必要です。また、AIはあくまでインターネット上にある情報を集めてくるため、インターネット上には出回っていない情報、例えば「採用の背景」「組織として何が問題になっているのか」「問題を解決するためには何が課題なのか」というような情報については別の手段で取得する必要がありますが、そこは従来の検索エンジンによる情報収集と同じ課題感と言えるでしょう。
■転職エージェントの活用ポイント
転職エージェントも活用する場合は、エージェントへの相談前にある程度情報収集をしておくと、より深い議論ができるかもしれません。
また、エージェントは企業の経営陣などキーマンに接触している可能性が高いので、インターネットには出ていない深い情報、つまり上記にもあるような「採用の背景」「組織として何が問題になっているのか」「その問題を解決するために何が課題なのか」や、企業の人事担当者や役員の方々などと直接会って感じた肌感・温度感・雰囲気・人柄などの情報を持っている場合もあります。また、企業側もまだ言語化できていないような課題や、そこからどのような人材要件を固めるか否かといったような内部事情まで把握していたりもするので、そういった情報はエージェントを活用して収集するとよいでしょう。
さらに一歩踏み込んで、それらの情報を鑑みて自分がその企業にどうマッチするのかをエージェントと議論し、企業側の課題に対して自分がどのように価値を発揮できるのかを整理しておけると、実際の面接の場でも質の高い時間となり、より良いマッチングにつながるかと思います。
AI×エージェントで“転職活動一歩目”を軽く — 最終的に活かすべきは専門家との連携

■AIだけで完結しない理由
より良い転職を実現するためには、企業課題やニーズの把握、経営側や人事側だけでなく現場メンバーへの理解、面接対策、年収交渉などの“生の情報のやりとり”が大事です。
エージェントは日々企業と相対し信頼関係を築いているので、上記のような情報のやり取りはエージェントを介することでスムーズになり、質も上がるかと思います。
また、面談などを通して応募者自身の人柄・志向性を深く理解するのはエージェントの得意分野なので、そういった意味でも企業側と応募者を深く理解するエージェントを頼ることは転職成功の大事なポイントとなり得るでしょう。
■AIとエージェントを併用するメリット
AIによって下調べや書類作成を効率化し、エージェントからは内容のブラッシュアップや的確なアドバイスを受けることで、スピードと精度の両立が可能になります。
AIは大量の情報を収集・分析し、エージェントからはインターネットに出てこない企業ごとの情報を取得するなど、両者の良さをそれぞれ取り入れて転職に活用してください。
ここまでご紹介した内容を踏まえて、AIとエージェントの役割を整理してみましょう。
■生成AIパート
- 職務経歴書のたたき台作成
- 業界や企業の情報収集と分析
- 自己分析
ここからスタートすることで、転職活動における重要な準備の第一歩目を無理なく踏み出せるかと思います。
■エージェントパート
- 企業ごとの生の情報
- 自己分析支援
- 企業の課題×自分の強み(提供できる価値)からマッチングの可能性の議論
AIを活用した履歴書作成に加えてこれらを行うことで、より良い転職に近づけるのではないかと思います。
まとめ
転職活動において、生成AIは職務経歴書のたたき台作成や企業リサーチ、自己分析の効率化において非常に有効です。特に最初の一歩を踏み出す際のハードルを下げ、短時間で質の高い情報にアクセスできるのは大きなメリットです。
ただし、AIだけではカバーしきれない「対話を通した自分自身の深掘り」や「リアルな情報収集=インターネットでは検索できない情報」、そして自分の強みと企業ニーズ(解決すべき課題)のマッチングといった点では、人の力――つまりエージェントの存在を効果的に活用していくのが一つの打開策です。生成AIと転職エージェント、それぞれの強みを活かすことで、効率と精度の両立が実現できるので、よりご自身の強みを活かしたい方はこの二つの利用をお勧めします。
弊社レキサンでは、地域に根ざした転職支援を行いながら、応募者一人ひとりの志向や強みを丁寧に引き出し、企業とのより良い出会いをサポートしています。
AIをきっかけに「ちょっと転職のことを考えてみようかな」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。沖縄でのキャリア形成を、私たちが全力でサポートいたします。
ぜひAIとエージェントをうまく活用し、皆さんの転職活動をより良いものにしていってください。