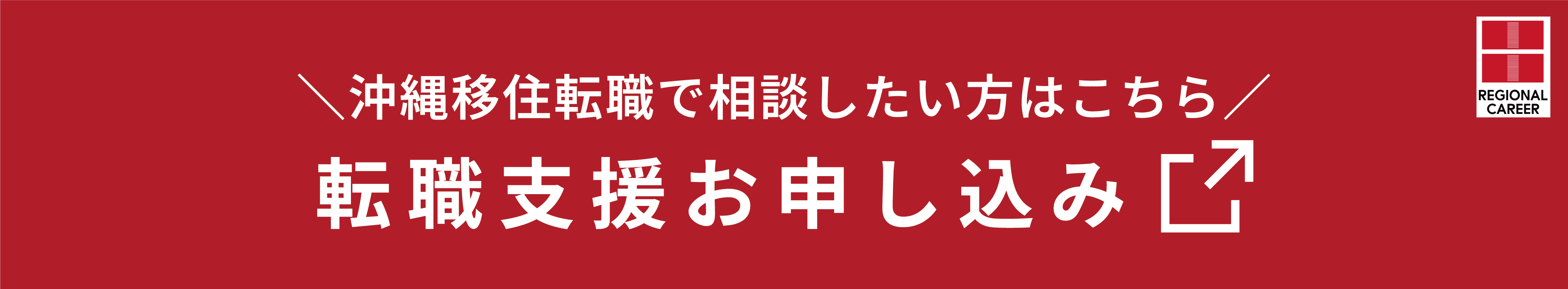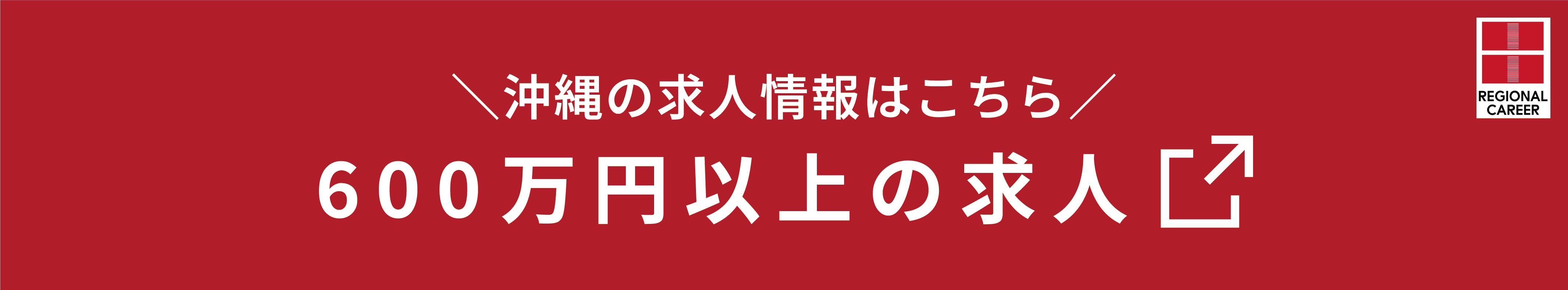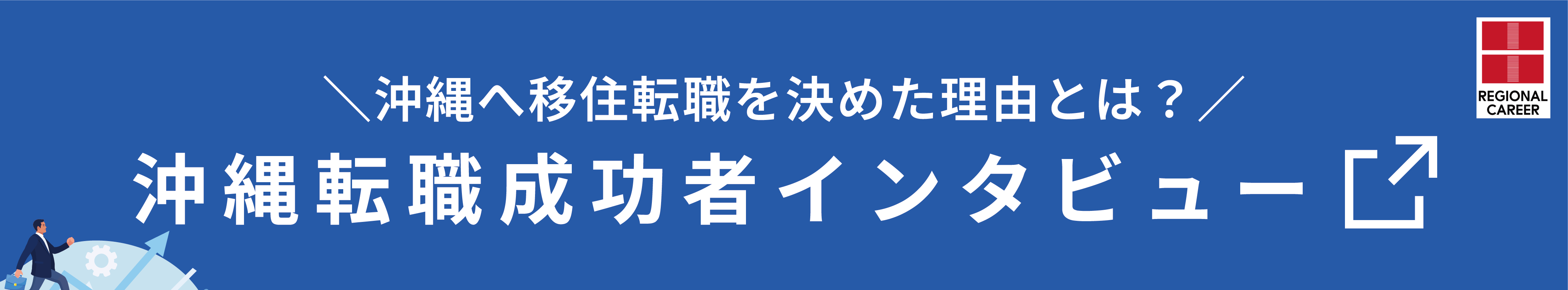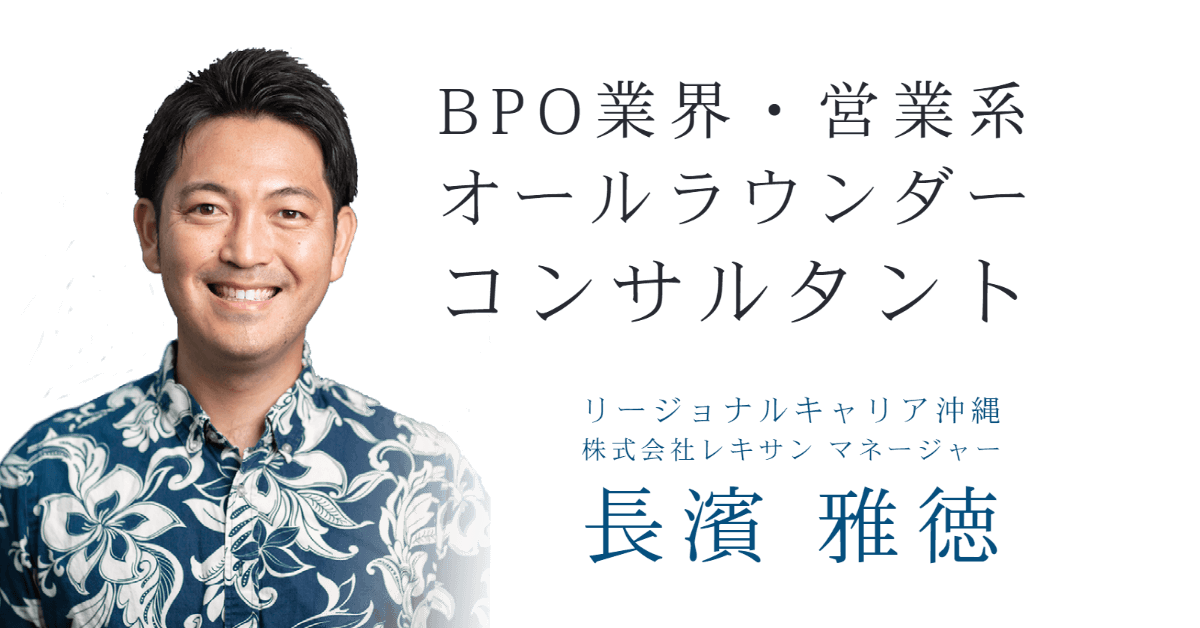【対談】東京から沖縄、そして世界へ――「東京都沖縄区」が広げるうちなんちゅの挑戦
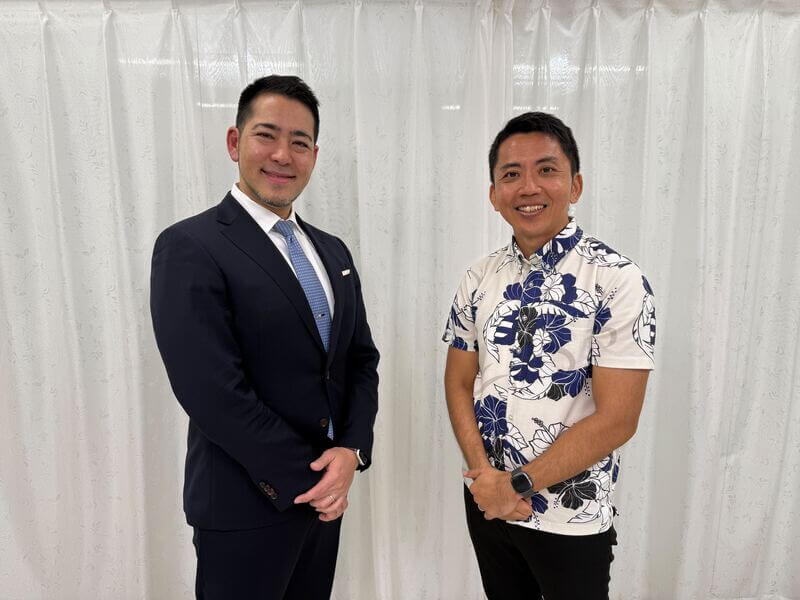
東京都で活躍する沖縄出身者の支援を目的としたコミュニティ「東京うちなんちゅ会」の代表を務める平良英之さん。今回は、平良さんの事業内容や宮古島から東京へ渡った経緯、「東京うちなんちゅ会」設立の背景と沖縄への想い、そしてこれからのビジョンについて株式会社レキサン社長の島村賢太と語り合いました。
今回の対談内容は、動画でも公開していますので合わせてご覧ください。
▼【沖縄×東京】東京から沖縄、そして世界へ―「東京うちなんちゅ会」代表・平良さんにインタビュー!
東京うちなんちゅ会—沖縄と東京をつなぐ活動
―上京支援とコミュニティづくり―
島村:本日は、東京で活躍されている沖縄出身者、いわゆる「うちなんちゅ」のお一人である平良英之(たいらひでゆき)さんにお話を伺います。平良さん、本日はよろしくお願いします。
平良:よろしくお願いします。
島村:まず、平良さんが今どんな事業や活動をしているのか簡単に教えていただけますか。
平良:私は合同会社東京都沖縄区という会社を経営しています。メイン事業は、企業の財務コンサルティングなんですけれど「東京と沖縄を盛り上げる」ことをコンセプトに、上京支援やUターン・Iターン支援、セカンドライフの相談にも取り組んでいます。 財務コンサルティングの業務の一環として、SNSで情報発信をしたりPRするということを行いながら、その知見を「東京うちなんちゅ会」に反映して発信する、ということを行っております。
もともと「東京うちなんちゅ会(東京都沖縄区)」は、東京に上京して活躍しているうちなんちゅ(沖縄出身者)をインタビューするところから始まりました。東京には多種多様な経歴のうちなんちゅが活躍していて、彼らをインタビューしてWeb上で紹介すれば、沖縄にいる人たちが「こんな仕事があるんだ」「同郷の先輩がやっているなら自分にもできるかも」と思えるきっかけになる。そう考えてインタビューメディアを立ち上げました。
その後、コロナ禍が始まって2年半くらい前に、ウェブ上でオフラインのような雰囲気のコミュニティを作ったらどうだろうと考えたんです。
島村:もともとインタビューメディアを立ち上げようと思ったきかっけはなんだったんでしょうか?
平良:仕事でインタビューをしていく中でいろんな人と出会い、僕自身「こういう人がいるんだ」「こういう働き方があるんだ」という発見が沢山ありました。その中でも、特に沖縄の人がいると「どういうきっかけでこんなキャリアになったんだろう?」という興味がわきました。でも、突然理由を聞くわけにもいかないので、ウェブメディアで情報を発信しているということにであれば相手も話を聞いてくれる。それがきっかけでした。
島村:実際、東京で活躍をしているうちなんちゅは多いのでしょうか。
平良:すごく多いと思います。たとえば全く知られていないけれど、JR東海の鉄道保守メンテナンス系の会社を創業したのが沖縄の女性だったり、ナンセイという産廃処理業者もそうですし、与那国島出身で電気のOEMを受注する会社を起こしたり、東京首都圏でも沖縄出身者でいろんな方が起業されています。
こういった流れでまずはインタビューメディアを始めたわけなんですけれど、それだけだとあまりにもニッチ過ぎて見ていただきにくい。 首都圏には沖縄居酒屋や沖縄関連のイベントがすごく多いのですが、点在していて知っている人だけがアクセスできるというもったいない状況だったんです。そこに“横串”を差すような役割を果たせば、もっと多くの人が情報を得られ、沖縄に触れてもらうことができるし、繋がりも広がり交流ができ、情報収集ができる。これが沖縄を盛り上げる活動になるかなと思いました。
島村:LINEのコミュニティがもうすぐ2000人、YouTubeチャンネルでは有名な沖縄出身アスリートや芸能関係者を紹介していますよね。
イベントも定期的に開催しているそうですが、具体的にどういったことを行っているんでしょうか。
平良:いろんな属性の人たちが集うコミュニティなので、酒造メーカーやオリオンビールさんに協賛いただいてエイサーのプレイベントをしたり、沖縄のバスケットボールチーム・琉球ゴールデンキングスの応援会を開いたり、スポーツやイベント、ビジネスの交流の場としてなど、幅広く行っています。
島村:沖縄県人会など様々な団体がある中で、東京うちなんちゅ会の強みとはなんでしょう?
平良:実際、首都圏にはたくさんの沖縄関連の団体があるのですが、徐々に高齢化してきている団体も多いです。若い人に向けて、私たちはWeb上での発信力を活かして、それら団体の活動を多くの方に知ってもらうゲートウェイとしての役割を担えたらと思っています。
島村:東京うちなんちゅ会では沖縄出身者同士で集まるイベント開催の他にも、上京支援のサービスもいろいろされているそうですね。
平良:はい。住まいの面では、不動産の仲介です。物件を紹介したり、上京してくる人にぼったくってくる業者も一定数いるので適正な金額になるようサポートしたり、初期費用を抑えて上京のハードルを下げてあげることで生活費にも回せるようにしたりしています。
宮古島から上京—東京に出ると決めた理由
島村:平良さんは宮古島ご出身ですが、それまで宮古島か沖縄本島で暮らす人生を想定していらしたのでしょうか。
平良:生まれも育ちも宮古島で、家系の長男という立場でもあり、いつかは宮古島に戻るんだろうなと思っていました。宮古島には高校までしかないので大学進学で沖縄本島に出たんですが、宮古島に戻るために安定した職業が何か考えたときに、公務員だと思いました。歴史が好きだったので、高校の地理歴史の教師になるつもりでした。実際、教育実習にも行きました。
ですが、そのときの担当教員から「どうせ社会科を教えるなら、県外に出て視野を広げてから教職員になった方が面白い話ができるんじゃないか」と言われたんです。確かにそうかもしれないと納得しまして、大学4年の就職活動の時期に「本島も東京も同じ“島の外”だから、どうせなら東京に行ってみよう」と決めました。
島村:ご両親やご家族は反対されなかったんでしょうか。
平良:両親も本土(県外)を一度経験して働いてから戻って来たので、「ちょっと経験するには良いんじゃない?」ということでした。 ただ、一生住むとこじゃないよとは言われました(笑)ま、自分もちょっと社会経験積むなら帰って行くか、という感じでした。
キャリアの転機—六本木での衝撃の出会い:東京で活躍するうちなんちゅ
島村:最初はどんなお仕事をされていたんですか。
平良:大学の同期が内定をもらったスーパーの会社に就職して、野菜や果物の仕入れ販売とかから始まりました。ところが、仕事終わりに六本木でバーをやっていた幼馴染のところに行くと、外資系金融やファンド、不動産投資、IT系など、沖縄では聞いたことのない業種の人がゴロゴロいて衝撃でした。IBM本社から来ている同い年の方が赤坂のタワーマンションに住んでいて、そこから東京タワーが見える景色を見せてもらったときには本当にびっくりしました。 沖縄にいる時の私の職業選択肢って、公務員や先生くらいしかイメージになかったんです。でも実際には自分が知らないだけで、「世の中にはこんな働き方があるんだ」「こんな世界があるのか」とわかってから目が覚めた感じで、もっと視野を広げたいと思いました。それから自分も金融系やコンサルに興味を持つようになり、ウェブマーケットだったり、いろんなところを転々として今の会社になっているという形です。
島村:宮古島で考えていた「公務員か教員」という選択肢だけでは知り得なかった世界ですね。
平良:そうなんです。僕自身が東京に来てきて、いろんな人に出会っていろんな選択肢を経て今に至るので、今沖縄にいて自分の周りの選択肢から「本当にこれでいいのかな?」ともやもやしている人たちへのチャレンジづくりができればいいと思いますね。
島村:それが上京支援につながる原体験でもあるのですね。
故郷・沖縄への恩返しと沖縄出身者の居場所づくり
島村:平良さんの活動からは、沖縄への強い想いが伝わってきますね。
平良:東京に出てきた時に、沖縄出身であることをポジティブに受け入れてもらえることが多かったんです。他の県だったら、ここまで受け入れてもらえなかったかもしれません。沖縄出身の先輩たちも、温かく迎え入れてくれました。 その一方で、そうしたご縁に恵まれず、本当はもっとやりたかったけど沖縄に戻ったという人を何人も見てきました。そうした違いは、サポートしてくれる人がいるかどうか、出会えるかどうかで生まれると感じています。だからこそ、私はそういった出会いをつくりたいと思っています。そしたら東京に残りたい人は残れるし、やりきった人はポジティブな意味で戻れればいいと思っているので。そういうことができれば、いろんな先輩から受け継いだ恩を後輩につなげられるというか。
島村:先輩たちから受けた恩を、今度は後輩に繋いでいきたいという想いなんですね。
平良:はい、そうです。60〜70代の先輩たちは、沖縄出身であることで差別的な扱いを受けることもあったそうです。だからこそ、沖縄で団結して頑張ってきた。私たちは、そうした先輩たちの苦労があったからこそ、恵まれた環境で育つことができました。 上京してポジティブに迎え入れられた人たちも、馴染むのに苦労している人たちもいるのでそういった人たちをうまくサポートできればと思っています。
島村:平良さんご自身も、いつか沖縄に戻られるのでしょうか?
平良:はい。もともと会社を立ち上げたのも、いつか沖縄に戻るとなった場合に会社員だと戻りづらいと思ったからです。沖縄と関わる仕事をしていれば、何かあれば仕事で沖縄に戻って生活自体を沖縄にすべて移さなくてもいいですし。
今はリモートワークも普及し、沖縄にいながら東京の仕事をすることも可能になりました。1年のうち1ヶ月くらいは宮古島で過ごしています。4回に分けて、1回1週間くらい家族と一緒に帰っています。子供がまだ未就学なので、今のうちに両親と会わせてあげたいと思っています。
島村:平良さんから見て、沖縄にはどんな魅力がありますか?
平良:島にいる時は当たり前すぎて分からなかったのですが、食文化や文化や伝統芸能、そして温かい人々。一番端という立地でもあるので「言葉も通じる外国」というような異国情緒感も良さの1つだと思います。そうした魅力に、東京に着て初めて気づかされました。例えば、海、島、砂浜一つとっても、東京とは全く違います。東京で勝負できるものが沢山ある、すごく魅力・ポテンシャルあふれる島だなと思いました。砂浜一つとっても違う。
未来への展望—沖縄から東京、そして世界へ―
島村:今後、沖縄にどのように貢献していきたいですか?
平良:うちなんちゅがチャレンジしたいと思った時に、「こうやったらここにアクセスできる」という道筋を示せるような存在になりたいと思っています。 沖縄県を離れてすごく感じるのが、沖縄県の持つ強さ・可能性です。沖縄県は琉球王朝の時代、万国津梁の精神でアジアと日本本土を繋ぎ、すごくグローバルに活躍していたなと。そのアイデンティティは、今も沖縄に残っていると感じています。県外に出れば出るほど、世界中にうちなんちゅのネットワークが強固に広がっていることを知り、これは万国津梁の現代版だと感じています。東京と沖縄の架け橋となり、私も世界で活躍するうちなんちゅをサポートしていきたいです。
最近決めたコンセプトは、「沖縄発、東京経由、世界へ」です。
島村:そう思うようになったきっかけは何だったのでしょうか?
平良:WUB(Worldwide Uchinanchu Business Association)という団体を知ったことをきっかけに、世界で活躍するうちなんちゅのことを知ったことです。(※WUB:世界中にいるうちなんちゅのビジネスマッチングを行い、海外進出を支援するなどの活動をしている)ハワイの知事が沖縄の人だったり、沖縄出身者で事業を成功させている人がいたり、「沖縄の人ってちょっと日本人と違って独特だよね」という認知をされている部分があるんですよ。 いろんな都道府県から移民が行っていますけど、他の地域の人たちは現地に同化する中で沖縄だけは沖縄の源流が残っている。「これぞうちなー魂だな」と。
島村:逆に沖縄本島に住んでいる我々よりも、むしろ外に出て行った人から学ばされることも多いですよね。 平良 そうですね。そういうのを知ると、やっぱり外に出るから大事にするというか。足元に合ったら、三線も弾かないですし。
島村:なぜ外に出ていった沖縄の人たちは、他の都道府県と違って沖縄の文化を残し、大切にしていくんでしょうか。 平良 いちばんの理由は、こっち(東京)で県人会が盛んだったように、他の地域の人と沖縄県民の間では同じ日本人でも差別があったようです。他の人と交わらず、沖縄の人は沖縄の人で集まった結果、それが団結力となり各地で成功者が増えるとそこにうちなんちゅたちが集う、というさらなる団結力に繋がったのではないでしょうか。 そういった人たちの、移民一世の人たちの話を聞くと苦労も多そうで、その血のにじむ努力のうえに私たちの道が繋がっているのだと思うとその流れを繋いでいきたいなと思いますね。 島村
海外で活躍されているうちなんちゅでいうと、アップル本社でスティーブ・ジョブズの下で働いたジェームズ・ヒガ(James Higa)さんなど、「沖縄系」として世界で活躍している人はたくさんいますよね。 平良 そうなんです。いざ一歩を踏み出してみて、「意外と自分と同じような人がいるな」と知ればさらに勇気になる。
島村:その「一歩を踏み出す」ということで大事になってくることはなんでしょう?
平良:いきなり就職で外へ出るという、重い決断をしないといけないですが、その一歩のハードルをさげるために去年行ったのが「東京ワーホリ」です。
「東京ワーホリ」プログラムと今後の展望
平良:まずは沖縄の大学生などが夏休みや春休みに2週間~1ヶ月滞在して、いろんな人と交流してみる。そうすることで、自分に合うと思えば翌年の就活を東京でもすればいいし、無理、合わない!と思ったら地元の沖縄で就職するという自己決定ができる、試すことができる。その「試す場」が必要だと思っています。 島村 今の話も含めて最後に、東京都沖縄区(東京うちなんちゅ会)として今後やりたいことやビジョンを教えてください。 平良 東京に来て、きっかけを掴めた人たちを沢山見てきたので、そういった人たちを沢山生むために東京体験を積極的にこれから実施したいです。いろんな人がチャレンジする受け皿を作り、ゆくゆくはそこでいろんな活動をした人が沖縄に戻ってやりたいことをやれるというようなコミュニティを運営していきたいと思いますし、世界へ活躍意欲がある人にはその機会を提供できるようなプラットフォームの場でありたい。 そういったことに力を入れていく年でありたいなと思っています。
島村:私たちレキサンも「沖縄に戻って活躍したい人のサポート」という動きに力を入れようとしているので、上京支援・セカンドライフ支援をされている「東京うちなんちゅ会」さんとぜひ協力していきたいと思っています。
本日は大変勉強になるお話をありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
平良:こちらこそ、よろしくお願いします。ありがとうございました。
まとめ
「家業を継ぐために早々に地元へ戻るはずだった」という平良さんが、東京で多様な価値観やキャリアの可能性に触れたことで、沖縄と東京をつなぐ事業を始められたのはまさに“出会い”が人生を変えた例といえます。
東京うちなんちゅ会や「東京降り」のプロジェクトなど、実際に体験し、人とつながることで新しい道が開けるというメッセージが伝わります。
レキサンでも、沖縄や東京、さらには世界を舞台に活躍したい方々をサポートしています。沖縄にルーツがある方はもちろん、地方出身で首都圏でチャレンジしたい方なども、ぜひ一度ご相談ください。
それぞれの夢が“東京経由、世界へ”と広がっていくようなきっかけになれば幸いです。
レキサンでは、U・Iターン転職やキャリア支援に関する無料相談も実施中です。どうぞお気軽にお問い合わせください。