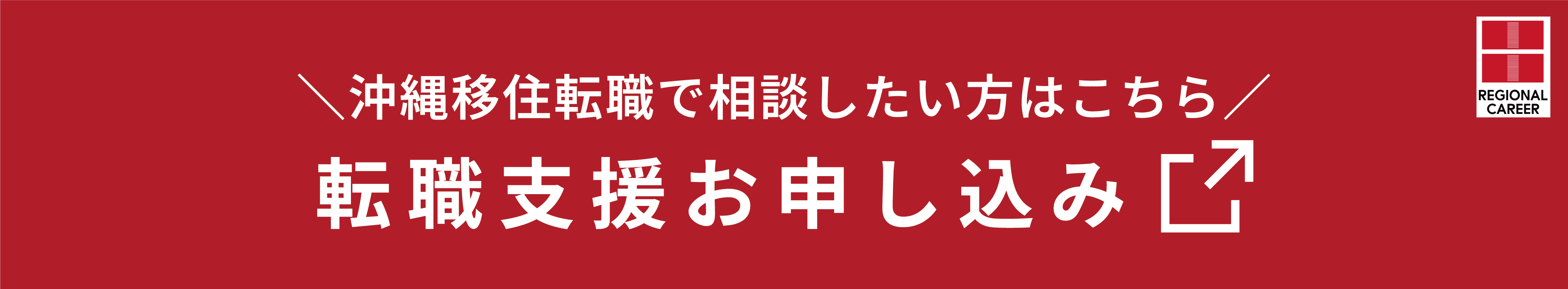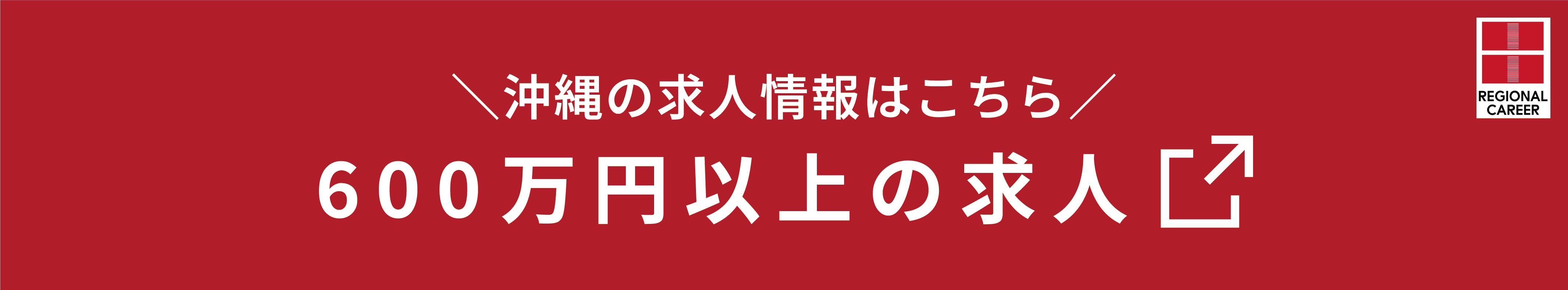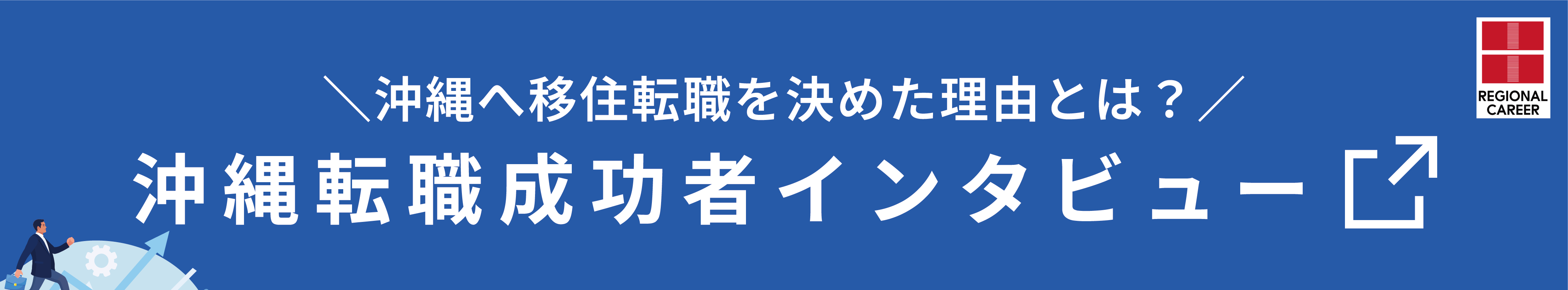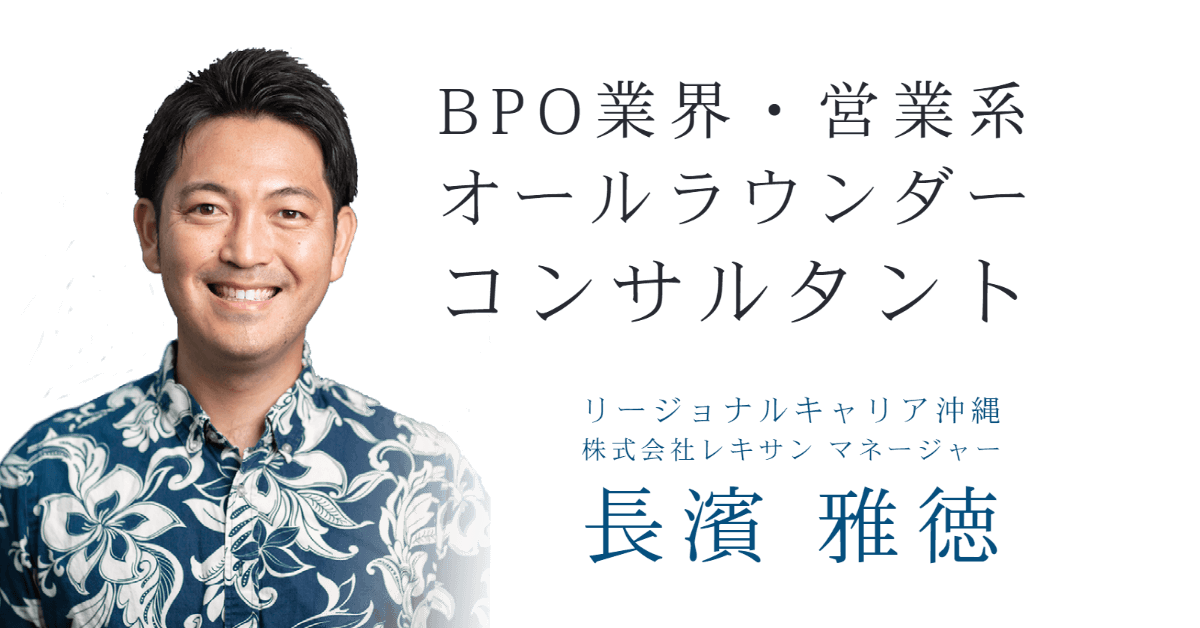沖縄の歴史から働き方の変化を読み解く~県外・世界のうちなんちゅ達~
こんにちは。株式会社レキサンのスタッフです。
沖縄の「県外で働く」文化について、皆さんご存じでしょうか?
沖縄では、昔から就職や仕事を求めて地元を離れ、県外で働く人が一定数存在してきました。その背景には戦後の米国統治や本土復帰による経済格差、さらには独自の歴史的・社会的要因があります。本記事では、沖縄の「県外就労」文化が形成された歴史的背景とその変遷、そして現代における経済事情やリモートワークなど新たな動きまでを詳しく解説します。
沖縄の「県外で働く」文化と歴史的背景

沖縄の県外就労文化は、単なる就労移動を超えた社会経済現象として定着してきました。戦後の米軍統治や1972年の本土復帰後も続く経済格差によって、「地元を離れて収入を得る」という選択肢が長期間にわたり当たり前だった時期もあります。特に高度経済成長期には、本土(沖縄県外)の都市部における労働力不足を補う形で、沖縄から大量の若者が移動しました。
こうした動きの背景には、個人の希望だけではなく、歴史的・構造的な経済格差がありました。1920年代に「ソテツ地獄」と呼ばれる深刻な経済危機を経験したことも、海外移民や県外就労という移動パターンを後押ししたとされます。さらに、本土復帰から50年以上経過した今でも、沖縄の県民所得が全国最低水準にとどまる現実は、この文化が継続する理由の一つといえるでしょう。
沖縄の県外就労文化—歴史的背景
ハワイや南米など海外への移住
―世界で活躍するうちなんちゅたち―
沖縄の人々の移動先は本土に限らず、戦前・戦後を通じてハワイやブラジルなどへ大規模な移民が行われました。1920年代、製糖業の経済崩壊による構造的な経済恐慌を指す「ソテツ地獄」(貧困のため食用ソテツの実を食べざるを得なかったことから)が有名ですが、これを機に家族ぐるみで海外へ移住するケースが目立ち、現在でも沖縄系コミュニティが世界各地で根付いています。これは本土への出稼ぎが一時的な移動になりがちなのと対照的に、永住を前提とした移民が多かった点が特徴です。
また、このような歴史を通して今に至るまで、沖縄から海外へ移住した人々は世界各地でコミュニティを形成し、特に「沖縄県人会」と呼ばれる組織を中心に伝統芸能・祭り・スポーツ等の活動を通じて現地社会とのつながりを深めたり、また起業して成功を収めたり大手企業で活躍したりしている人たちも少なくありません。
戦後復興期から本土復帰前後まで
第二次世界大戦後、沖縄は1972年まで米国の施政下にあり、本土とは異なる通貨や貿易体制が続きました。これにより輸入依存型の経済構造が形成され、工業化が遅れたまま本土復帰を迎えます。1972年の復帰後、インフラ整備や公共事業への巨額の補助金は投じられたものの、本土企業が大規模受注を行うなどして地元経済への恩恵は限定的でした。この結果、より高賃金や多くの雇用を求めて県外へ移る若者が増加し、沖縄の出稼ぎ文化を定着させる大きな要因となったのです。
1960〜70年代に広がった県外就職の現状
本土では高度経済成長期に、建設業や工場勤務の人手不足が深刻化していました。これを補うため、沖縄本島はもちろん、八重山や宮古といった離島からも多くの若者が大都市へ移動し、県外就職が加速しました。インフラ整備、特に道路建設などを中心に沖縄の開発が行われ、1975年の沖縄海洋博覧会に伴い建設業、観光業、流通業が急拡大するなどの大規模な公共事業による「本土との格差是正」は一部で進んだものの、大企業の下請け構造などから地元への波及は限定的だったとされ、県外志向が依然として強まります。
このように、沖縄の「県外で働く」文化は、戦後の米国統治や本土復帰後の経済格差といった、長く複雑な歴史的背景を背負って現代に至るまで続いています。戦後から高度成長期までの大規模労働移動は、個人の意欲以上に構造的な要因が強く働いたといえます。
[参照:『第2次世界大戦前の沖縄県からので稼ぎについて』『沖縄における移民・出稼ぎ教育』]
現代の県外就労事情と課題

前章では沖縄の「県外で働く」文化が形成された歴史的背景を見てきました。
では、現代の沖縄県外就労にはどのような問題や変化が生じているのでしょうか。ここでは、現状の課題や新たな対応策について詳しく掘り下げていきます。
現在の県外就労事情:背景と変化
沖縄の雇用・賃金水準と若年層の都市部流出
本土復帰から半世紀が経っても、沖縄は製造業の比率が全国平均の約5分の1(4.3%)にとどまり、安定的な雇用を生む大企業や工場が不足しています。また、観光・公共事業・基地収入に依存する「3K経済」と称される構造は、県民所得を押し上げにくい要因です。米軍基地がもたらす雇用や経済効果は、実際に既返還駐留軍用地跡地の直接経済効果として返還前の89億円/年から返還後は2,459億円/年に増加し、雇用者数も327人から23,564人に増加しているという大きな効果を確認できるデータがある一方、こういった現状への依存が他産業の成長を阻害しているとの指摘もあります。
こうした背景から、進学や就職を機に県外へ出る若者は今も多く、例えば石垣市では高校卒業時に進学や就職に伴う転出超過が見られ、男女ともに15〜19歳、20〜24歳にかけて発生しています。本土での多様なキャリア機会を求め、地元に戻らないケースも少なくありません。親の介護や家族の事情でUターンを検討しても、自分のスキルを活かせる職場が県内に乏しいと感じる人も多いのが現状です。
県外就労の多様化
コロナ禍でリモートワークが広がる中、沖縄在住のまま本土や海外企業の業務をオンラインで担う「リモート出稼ぎ」が登場しました。また首都圏などの企業でフルリモートワークの働き方が可能になり、転職をせずとも、給与水準の高い県外本社の企業に就労したまま沖縄にUターン・Iターンの移住ができるようになりました。これまでの物理的移動を伴う出稼ぎとは異なり、県外に行かずとも収入を得られる新しい就労形態です。県や自治体がコールセンターやIT系企業を誘致し始めた動きも相まって、“外に行く”だけではない多様な働き方が沖縄に根づきつつあるといえます。
県外就労文化の影響と産業の多角化
若い世代が県外就職を選ぶことで、農林水産業や伝統行事の担い手不足の一要因になっていることも考えられます。特に離島部では人口減少と高齢化が進行し、地域コミュニティや経済の停滞が懸念されており、復帰前後と比較するとサトウキビやパイナップルの生産は大幅に減少するなど沖縄の農業や特産品が衰退していっている状況にあるのは大きな課題です。また、地域の伝統芸能や祭事の承継の担い手不足により、地域固有の文化が消滅していくという現実もあります。
沖縄では、観光・基地関連に依存する経済構造から脱却し、ITや製造業など新たな産業の育成が必要だと長年指摘されています。2020年度の自主財源比率が33.1%と全国平均43.6%に比べ大きな差があるなど、“3割自治”の財政構造では地域経済を多様化させるための施策が打ちにくい課題も残ります。そんな中、近年では県外で得た経験・スキルを活かすUターン就職が徐々に増えてきています。また、コールセンター誘致や情報通信産業の進出に加え、創業支援やスタートアップ育成に取り組むことで、高付加価値の仕事を地元に作る動きも始まっています。こうした産業の多角化が進めば、県外就職の必要性そのものが減少し、沖縄の若者の県内定着が促される可能性があります。
そして、実際に沖縄県ではそういった新しい働き方や産業の取り組みも生まれています。
次章では、リモートワークの普及やIT企業の誘致を中心に、沖縄が取り組む新たな可能性と今後の展望を探っていきます。
[参照:『駐留軍用地跡地利用に伴う経済波及効果等に関する検討調査』 りゅうぎん総合研究所『沖縄県の主要経済指標』 読売新聞【基礎からわかる】沖縄の経済、どのような構造か? 第二期 石垣市地域創生総合戦略]
新たな動きと今後の展望

リモートワーク・ワーケーションと“逆流入”の兆し
沖縄に拠点を置く企業の増加
沖縄は東アジアの海底ケーブルなど通信インフラを整備し、県がIT企業やコールセンターの誘致を積極的に進めています。例えば、沖縄県内の情報通信関連企業数は令和4年度時点で943社で、うち県外からの立地企業は531社、雇用者数は約4万人とされているほか、沖縄県が整備した「沖縄IT津梁パーク」では7棟の企業集積施設が供用をはじめ43社が入居、約2,600人の雇用を創出しています。成果はまだ観光業に及びませんが、情報通信関連産業は県内で急速に成長しており、特にソフトウェア開発やコンテンツ制作など高付加価値分野への進出が進んでいます。専門性の高い職種を沖縄で確保する道は拓けつつあると言えるでしょう。コロナ禍におけるワーケーション需要の高まりもあり、観光資源を活かしたワーケーション推進も同時に行っていることからリゾート環境で働きたい人材を呼び込む動きが見えます。
リモートワークの普及とスタートアップ支援
リモートワークが定着すると、本土から沖縄への移住を選ぶ人も増え、“逆流入”“逆出稼ぎ”とも呼べる現象が起こります。コワーキングスペースやシェアオフィス整備が進めば、沖縄在住者が本土や海外の仕事をオンラインで請け負うだけでなく、外部からの移住者が沖縄を拠点に活動するケースも増えるでしょう。実際、沖縄県ではそれらの整備も進み始めており、リモートワーク環境の推進に向けて変化しつつあります。
また、ITやスタートアップ支援がさらに進めば、沖縄の産業構造は大きく変化するかもしれません。沖縄県内のスタートアップ企業数は2023年時点でおよそ100社ほどとされおり、緩やかに増加しています。沖縄県はさらに2028年までにスタートアップ数を200社に増やすことを目標に、例えば2022年には沖縄県知事が会長の「おきなわスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム」を設立したり、スタートアップ支援拠点として法人手続きサポート、起業支援金の受付、メンタリング、投資家とのマッチング、県外や海外への展開を支援する「Start up Lab Lagoon NAHA」が那覇市に開設されるなど、具体的な施策が進んでいます。海外展開という点では、例えば沖縄科学技術大学院大学(通称OIST)のイノベーションアクセラレーターは、世界中の起業家に最大1000万円の資金提供や先端研究設備へのアクセス、メンタリングを行い、沖縄から世界を狙える研究開発型スタートアップの起業を支援しています。
こういった新しい取り組みによって、これまでにない新たな職種・ポジションが増えていくと共に県外から沖縄へ働きに戻ってくる、或いは新たに移り住む人の増加が期待されます。 ただし、依然として国からの補助金や公共事業への依存度が高く、また物流コストが製造業や輸出入に影響を及ぼしている離島特有の現状と課題は残っており、県全体ではこれらの課題を踏まえた長期的視点での取り組みも産業構造の在り方を考えていく上では求められます。
[参照:沖縄県『令和4年度情報通信産業振興計画実施状況報告書』 沖縄県 企業立地支援 情報通信産業サポートガイド 沖縄県 商工労働部『令和5年度おきなわITセンサス報告書』 カヤックゼロ 沖縄スタートアップ図鑑]
まとめ
戦後の米国統治と本土復帰後の経済格差を背景に、沖縄では長らく「県外で働く」文化が続いてきました。近年はIT企業の誘致やリモートワークの普及によって、多様な働き方や“逆流入”の兆しも見え始めています。今後、観光・基地依存からの脱却と産業多角化が進めば、若者の県内定着と地域活性化に繋がることが期待されます。
沖縄の過去と現在を見つめ直すことで、UIターンや新しい働き方を考えるヒントも見えてきます。弊社レキサンでは、沖縄専用の転職エージェントとして、Uターン・Iターンを検討する皆様のキャリア形成をサポートし、沖縄での仕事や暮らしがより充実するよう力を尽くしています。
「沖縄へ戻りたい」「沖縄で新たな一歩を踏み出したい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。皆さまの夢と沖縄の未来をつなぐお手伝いができれば幸いです。
また、合わせて過去の関連記事もご覧ください。